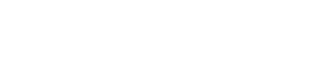もち麦の野性味と苦味、端正な豚肉の脂身の甘味。
対極の魅力が生きる、焼きリゾットとグリル
「元々、特に“体にやさしい”ことを意識したつもりはなかったんですが、食材を生かすことを考えているうちに、みなさんから“ずっと食べられる”とか、“やさしい味”というお声をいただくようになりましたね」
そう語るのは今回、塚田さんの「ゆたか農場」へと一緒に足を運んでいただいた【ビストロ・エミュリシエ】の吉田研シェフだ。元々、箱根にある名オーベルジュ【オーミラドー】から修業をはじめ、これまでに群馬県、長野県、都内、北海道など日本各地で料理をしてきた。奥様の地元である熊谷市に店を開き、今年で11年になる。
土地ごとに違う食材の多様な魅力に出会う中で、食材の力を一番に感じてもらうために、どう料理すればいいのか、料理人人生の中でずっと向き合ってきた。
今回は、そんな素材に実直に向き合う吉田シェフに、塚田さんの元へと訪れた後、「古代もち麦」を使って考案した料理を、3品つくっていただいた。

吉田シェフがまずつくり始めたのは、熊谷米豚「穀王」の肩ロースのグリルに焼きリゾットを添えた、メインディッシュの一皿。
まず、もち麦を混ぜた米を硬めに炊き、バターライスにした上でそれをリゾットにする。さらに表面をオリーブオイルでカリッと焦げ目がつくように焼き上げる。何度も火を入れる中でも、麦の芯が残るように細かく火を入れ、もち麦が持つ独特の食感と風味が感じられるように仕立てていくのだ。

主役は、熊谷のブランド豚「穀王」。飼料の75%以上をお米で育てられ、みずみずしいくらいのキレのいい脂身と濃い肉の旨みが両立する熊谷のブランド豚だ。
その肩ロースがしっとりとやわらかくなるよう、低温のオーブンでゆっくりと火を入れる。提供の直前には表面を網目状にグリルし、香ばしさを出していく。仕上げに、グリーンペッパーとはちみつ、マデラ酒を使った甘味とスパイシーな香りを纏ったソースを回しかけて完成。ソースの光沢と、その隙間に顔を出すロゼ色の肉の断面がなんとも食欲を誘う。

「歯がスッと入るくらいの柔らかな肉質と、込み上げてくるジューシーな豚肉の味。そして脂から染み出す甘味と対をなすのが、「古代もち麦」が持つほのかな苦味。対極にある味覚が両方際立つように、その魅力を見事に一皿の中で融和させていく。
「『穀王』のよさは、さっぱりとした脂なのに甘味がしっかりあること。野性味と苦味のあるのある古代もち麦を合わせると、両方のいいところが引き立ちます」
聞けば、箱根【オーミラドー】での修業時代に出会った当時のスーシェフを恩師と仰ぎ、同店を出たあとも懇意な関係が続いたという吉田シェフ。そのご縁で、西洋野菜や無農薬の野菜を育てる農家とレストランをつなぐ事業をしている方と知り合い、食材の扱い方をプロの料理人たちに教える専属料理人として活動していたこともあった。その経験の中で、食材が持つ魅力を見抜く力を養っていったのだという。
自家製パンチェッタ、温泉卵、チーズを包み込む、もち麦のガレット

2品目は、まだお店でも提供したことがないというガレット。蕎麦粉を使うのが一般的だが、粉末にした「古代もち麦」を使うことで、その魅力である力強さと風味を、よりダイレクトに感じられるようにと、考案していただいた。
「ガレットとは言いつつ、ガレットとクレープの合いの子のようなイメージです。もち麦の味を伝えたいので生地には甘みは入れてないですし、卵も控えています。最初に麦の香りがして、その後わずかにピリッとした苦味を感じると思います」
直径20cmほど、薄く焼いたガレット生地の中に、温泉卵にした埼玉県の彩たまごと、「穀王」を使った自家製パンチェッタを忍ばせる。上から、ハードタイプのチーズを削りかける。

フランスでは「卵、ハム、チーズ」でつくられるガレットを、「ガレット・コンプレット」という。「コンプレット」とは「完全な」「完成した」という意味で、味わい的にも栄養的にも抜群だとして食べられている。いわば最強の組み合わせ、と言って差し支えないだろう。
余分な脂を落として肉の旨みが凝縮されたパンチェッタと、濃い卵黄の味わい、チーズの香りとコク、そして、ベースとなるガレット生地の風味。それぞれの役割と魅力が明確で、それが渾然一体になる瞬間の喜び。食材数も少なくシンプルな仕立てでありながら、どれかが突出しすぎることなく味が融和する絶妙なバランスだ。

素材を生かす料理をめざす中で吉田さんが、たどり着いたのが「バターをほとんど使わないフランス料理」だった。例えばソースをつくるときに、クラシックなフランス料理ではバターは欠かせない存在だが、代わりにワインを通常よりも煮詰めるなどして、濃度を出すという。
「バターは、フランス料理の中で一つの文化ではあると思います。ですが日本でやるのであれば、バターを使わなくてもコクを出す方法やまろやかにする方法はあるなと思って。修業時代、日本料理、中国料理、イタリア料理の方々と交流する中で、そういう思いは強くなっていきましたね」
ライスプディング、シュー生地、キャラメルと
七変化するもち麦を楽しむ『リオレ』

最後の3品目は、なんと「古代もち麦」を使ったデザートだった。それも一皿の中でもち麦が、表情の異なる3つの仕立てで出てくるというから驚きだ。
メインとなるのは、お米ともち麦を混ぜ合わせたものを牛乳で炊いたライスプディング。フランスでは「リオレ」と呼ばれる伝統的なお菓子で、家庭的なデザートの一つ。
カクテルグラスに盛られたライスプディングに、【ビストロ・エミュリシエ】の庭で採れたという桑の実のソースを添える。さらに、もち麦生地でつくるプチシューをのせ、さらにもち麦のポン菓子をキャラメリゼしたプレートを脇から差し入れ、最後に彩りでミントの葉を一枚。

やさしい甘味のライスプディングは、日本人にとっては異国らしさが薫る食べ物かもしれない。だが桑の実のソースの香りが混じると、お米ともち麦の食感も相まって、道明寺のように、春らしくどこか懐かしい味わいになる。そこに、キャラメルプレートの大人っぽい苦さが綺麗なアクセントとして加わる。
サクッとした食感のプチシュー、ほろ苦いキャラメルプレート、そしてやさしい甘味のライスプディング。華麗なるもち麦の七変化が、楽しいデザートだ。
食材が持つ特徴こそが美味しさの原点

豊かな発想から、古代もち麦のさまざまな表情を引き出していく吉田シェフ。一つ一つの食材の味を丁寧に引き出していくことで、軽やかでありながらしっかりと満足感を積み重ねていく。料理をつくり終えたあと、改めてシェフに「古代もち麦」の魅力を聞いてみた。
「野性味と噛み締めたときの存在感、そして最後にほのかに残る苦味。最近では、こういう力強い食材を探すのは難しくて、僕たち料理人からするとありがたい存在です。えぐみも、苦味もひっくるめて、その食材が持つ特徴こそがおいしさ。熊谷でも塚田さんのような食材をつくる農家が増えているという話しは聞くので、料理人としては一つ楽しみでもあります。食材の“原点回帰”。だんだんそういう流れになってくれたら嬉しいですね」
取材・文/郡司しう 写真/清水伸彦