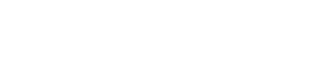革新的な販売方法と味でトップシェフを魅了、そして海外へ
こうして、独自のやり方で育ててきたチョウザメは順調に抱卵。6年で卵を持つシベリアチョウザメを中心に、2018年は11匹、2019年は39匹、2020年は60匹、そして2021年は90匹を出荷できるまでになった。
さて、製品にする工場がない中、出荷できるチョウザメをどう売ったのか。その販売方法にも大山さんのユニークなアイデアが炸裂する。なんとチョウザメごと飲食店に販売し、彼らに自家製のキャビアを作ってもらうという手法をとったのだ。
「みんな自家製を売りにする時代、自家製キャビアは飲食店の売りになると思いました。いくらだって、からすみだって、みんな自家製でしょう? キャビアも旬があるんですよ。旬のフレッシュな卵で塩漬けしたキャビアは本当においしいんです。キャビアの旬の味も知って欲しかったし、その時期に店ごとの味で自家製キャビアをつくっていただくことは魅力的だと思いました。物理的に2020年までは加工場もありませんでした。かといってOEMで外注して製品をつくることは考えなかったので、チョウザメごと販売する、というのが僕にとっても買っていただく方にとってもベストだと確信していました」

キャビアはチョウザメの大きさにもよるが、体重10%程度の卵をもつ。仮に10キロの個体だとすると1キロ前後のキャビアをつくることができる。加工賃などがのらない価格で卸せるため、店にとっても、製品のキャビアを購入するより、コストをかけずに仕入れられるメリットがある。
シーズンは、12月中旬から3月中旬までの3ヶ月。そこで仕込み、作ったものを冷凍しておけば通年使うことも可能だ。それはつまり、料理人が“おいしい”と思う塩分濃度のキャビアをたっぷり使うことが可能になり、ゲストにも喜んでもらえる、という三方良しの図式になるのだ。

販路を広げるために、大山さんは岐阜県から東京まで出向いた。そして“ここは”という店に予約をし、食事をして自身のキャビアについて料理人に聞いてもらう機会をつくっていった。話しをして興味をもってくれる料理人に卸していくうちに、さらにクチコミでじわじわと評判が広まるようになった。
「キャビアは輸入するもの、という世間の思い込みを払拭したい。そんな僕の気持ちに、“できるだけ日本の食材を使いたい”という料理人の方が興味をもってくださることも多いです。質が良くフレッシュなものが日本で手に入るのに、わざわざ輸入ものを使わなくてもいいですよね? 」
一匹ずつ販売先を探しながら地道に知ってもらう努力をして3年半。今では面識のない料理人の方からも連絡をもらうようになってきたという。
欧米への輸出を見据えてつくった、最先端の加工場

順調にチョウザメが育ち、抱卵したチョウザメの出荷数も増えてきた2020年2月22日、自社敷地内に加工場をつくった大山さん。
「このマーク、格好いいでしょう? チョウザメの英語”Sturgeon"のSと、僕の名前・晋也のS、それにチョウザメの形をかけて作りました。僕がつくった日本発の本物のキャビアの味を知って欲しいという思いを込めたんです」と嬉しそうにラボを案内してくれた。
このラボでは、世界基準の水産食品加工施設HACCPに沿った徹底した衛生管理を行っており、中では精密機械が作れるほどのクリーンルームとなっている。
「この室内は、ヘパフィルターをつかった空調で埃やチリを吸い取って外に出し、ウイルスが入らない最新の設備をいれています。この部屋には12月から3月に
卵を採卵し、キャビアの製品にする間だけ作業をする僕と妻の二人だけしか入りません」。



そもそも、HACCPとは2020年6月から食品を扱う全事業者に対して義務化された衛生管理の国際的な基準。有害な微生物や化学物質などが、原材料の段階から製造過程までで食品中に混入、増殖することへの悪影響を予測し、それを防ぐための方法をルール化する、というもの。
簡単に言えば製造工程を細分化し工程ごとのリスク管理をすることだが、ここでも、大山さんの負けず嫌いが顔を出す。そこまでクリーンな環境を作る必要はなかったが、やるなら徹底的にと、建設業で付き合いのあった理化学メーカーの力を借り、最新の機械を導入してどこにも負けないクリーンルームをつくってしまったのだ。


「HACCPを取り、これだけの高い基準をクリアしたラボを作ったのは、いずれ欧米に輸出したいとう気持ちがあります。初年度は5キロしか製品化できませんでしたから、数量はまだまだ。ですがこれからは、少しずつ製品化の量も増やしていきたいですね。数量が増えてきたら、輸出もしていきたい。そしてキャビア=欧米という概念を変えたい。日本でもこれだけ上質で美味しいキャビアがつくれるのだと勝負したいです」。
クリーミーでクリアな味、「晋也キャビア」の美味しさの秘密
大山さんは、繁殖、飼育、商品生産、そして販売まですべて一人で担当している。1000匹以上いるチョウザメの飼育、営業に、キャビアづくりなど、話を聞けば聞くほど一人で切り盛りしているとは、にわかに信じがたい仕事量だ。
人を雇わない理由を聞けば、「なんでですかね? 魚が好きで好きでしょうがないということと、突き詰めないと気が済まない性格なんですよ。寝ても覚めても魚のことばかり考えているんです。こんな変人について来れる人、いないでしょう?」と笑った。
そうしたこだわりは、しっかりと味の面にも反映されている。その味の良さは、トップシェフたちがこぞって使っていることからも証明されるだろう。それはやはり、独自で編み出したチョウザメの育て方、管理方法から生まれているものだ。

大切なことは、毎日注意深くチョウザメを観察し、環境を整えること。例えば、3月から梅雨明けの7月頭くらいまでは、チョウザメに餌をやり、7月中旬から9月は水温が上がり、酸欠になりやすいので餌はやらない。水温が下がり始める9月からまた餌を与える。さらに、水温が下がってきて代謝が落ちてくる11月から再び餌止めをし、12月からは出荷池で管理する。そして12月から3月までしか採卵しない。自然のサイクルに合わせて細やかに調整した、健康的なチョウザメは良質な卵を持つ。
卵を抱いたチョウザメは生きたままラボに運び、腹を割いて丁寧に卵を取り出す。手作業で卵をほぐし、2.7%の塩分で漬け、電磁波をかけながらドリップを出さない特殊凍結でキャビアを冷凍。こうして自社のキャビアは誕生する。
出来上がったツヤツヤと輝くキャビアは、まさに“黒いダイヤモンド”という異名にふさわしいオーラを放つ。食べてみると、クリーミーなコクがありながらしつこくない。クリーンで清らかな岐阜県の水で育ったことを想像させるキレイな味だ。
「加工場ができたことで、お客様の要望に合わせて塩分濃度を調整し、OEMでキャビア生産の請負もできるようになりました。自社製品はふるさと納税でも販売しています。これからは輸出に向けた道筋もつけていくつもりです」と大山さん。
これからは、キャビアの種類も増える予定だという。来年は、岐阜県初のオシェトラのキャビアを出荷ができる見込み。さらに、国内ではまだ生産実績がないというベルーガは10年後に卵を持つ予定だ。
また、日本にはまだまだ浸透していない国産キャビアとチョウザメの良さを知って欲しいと、キャビアをたっぷり食べられるオーベルジュも敷地内に来年オープン予定。大山さんのチョウザメを愛する情熱は、さまざまな形となり、日本中にそして世界に広がっていく予感だ。
撮影/今清水隆宏 取材・文/山路美佐